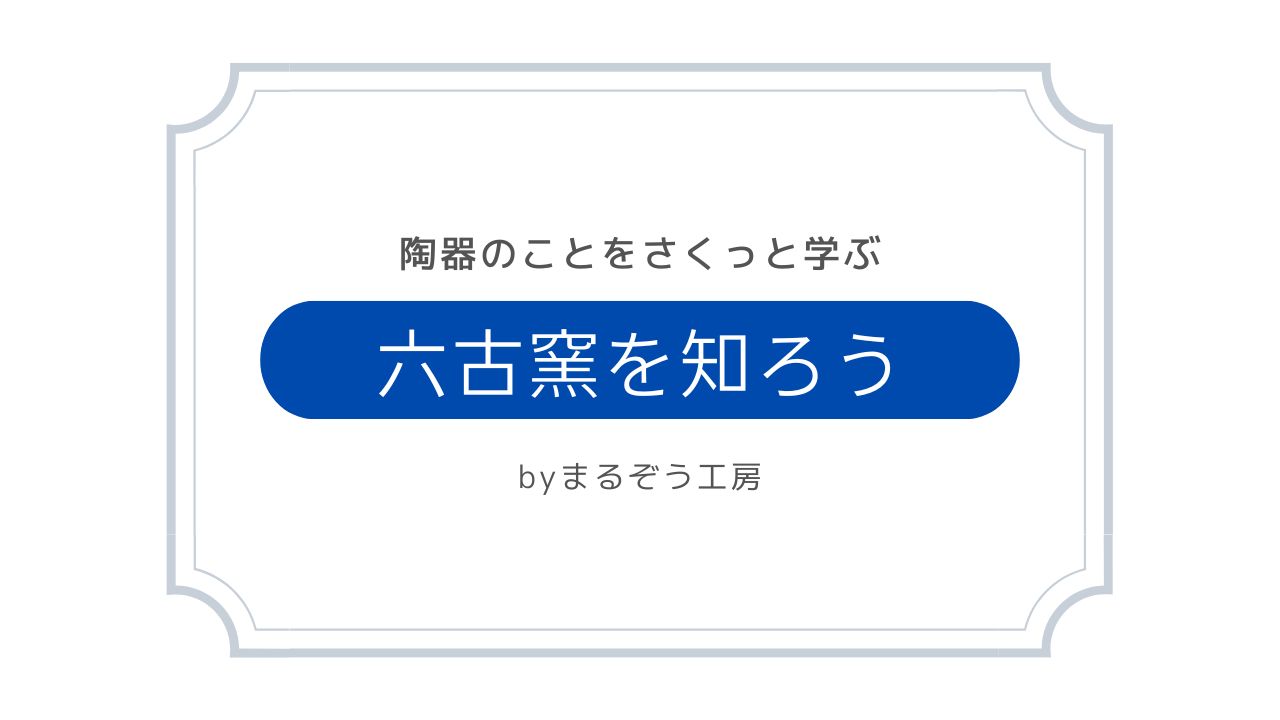読みやすい本が多くなりましたね
最近出版される本は、どれもとても読みやすくなっているように感じます。中身の構成にも時代の流行があるのでしょうか。字も大きかったり、見出しごとに分かれていたり。それに比べて昔の本は正直読みにくい。小林秀雄の「考えるヒント」なんて、読もうと思ってもいっこうに進みません。日本語を読んでいるし、確かに読んでいるんだけれど、全く頭に入ってこない。そもそも”頭に入る”と言う現象は、科学的に言うと何が起きているのでしょうね。頭に入っていなくても読んではいるんです。別に声に出して読んでも良いです。けれど全く身になっていかない。不思議です。

話が逸れたので戻りますが、読みにくさの正体の一つは、言い回しとでも言えばいいのでしょうか。日本語の使い方が難しい、一つのセンテンスも長くって、例えば「それについては」と言った言葉が出てきたときに、その「それ」はどこの事なのか。そこで取り上げたいものは以前の内容のどこにかかっているのか。勿論そんな作業は本を読む上で当たり前のことだと思うのですが、それがかなり前の部分であったり、とにかく分かりにくい。そう言う事を考えながら、あちこち戻りながら読んでいかないといけない。中学生や高校生の頃の現代文のテストで、まさにこう言う事をやらされていたなと思い出します。苦手でした。
ところが今の本は読みやすいものが多いです。例えば「葉隠」の現代語訳にしても、三島由紀夫の「葉隠入門」よりももっと時代を下って出版された現代語訳の本の方が読みやすい。また数年前には「超訳」とタイトルについたシリーズを本屋さんでよく見かけました。全部読まなくっても、美味しいところだけをつまんで味わえるようにしてあります。よく言えばカジュアルと言うか、入り口を広くしてくれているので入りやすい。でも見方を変えるとインスタントとも言えそうです。
確かに昔の本よりも今の本の方が読みやすいし理解しやすい。だけどそれで本当に良いのかなぁ、と思うんですね。もちろん全てではないですが、極端に言うとどんどん子供向けの様になっていっている気がします。
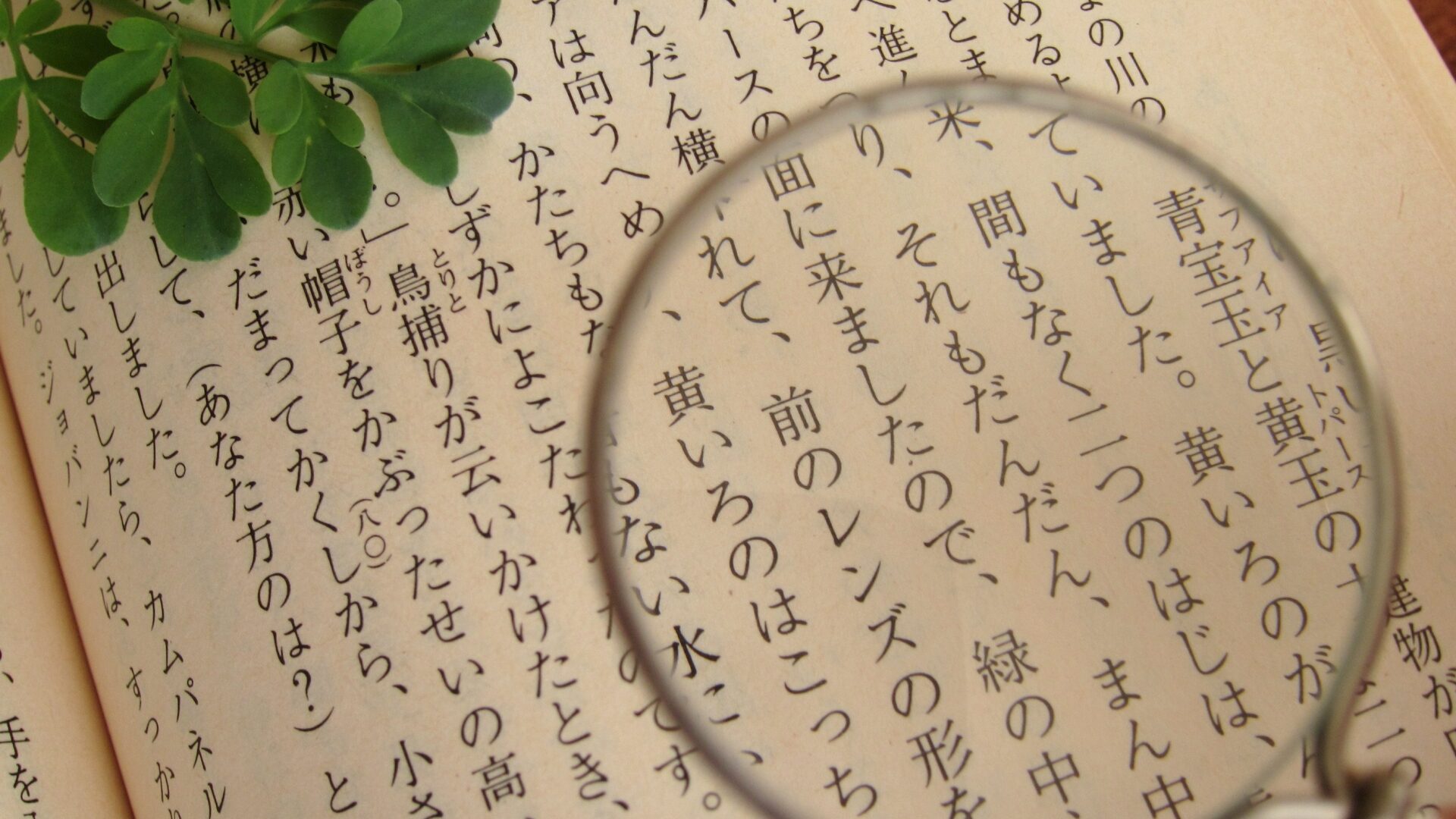
「読解力」って、いったいどういう力なんでしょう。文章を読んで正しく理解し、熟考する力だと言いますが、それだけなのでしょうか。例えば相手の気持ちを察するスキルや自分の考えを分かりやすく相手に伝えるスキルって、関係はないのでしょうか。どうなんだろう。また今の大人も昔の本をどんどん読めなくなっていっているのだとしたら、それは何を意味するんでしょう。文章に日々触れる人間への影響もそうですが、日本語としての変化と見てもどうなんだろうなと思ったりします。古典はもう専門家でなければ理解できません。字さえも読めません。古典まで遡らなくっても、例えばサザエさんの初期の漫画を読むと、今では使われない文字の表現が出てきます。そして戦後には「国語改革」みたいなものが国主体で進められたそうですね。
日本語がどんどん簡単になって行きます。それは使われない言葉や表記、慣習が生まれていくという事。つまりどんどん文化が無くなっていくと言える気がします。大丈夫なんでしょうかね。なんとなく良くない事のように感じるので、機械があれば福田恆存さんの「私の國語教室」でも読んでみようと思っています。難しそうだなぁ。